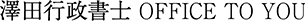遺言書の作成方法とは
- コラム

遺言書の作成は、遺産相続に関するトラブルを未然に防ぎ、自分の意思を正確に伝えるために非常に有効な手段です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは、自筆証書遺言と公正証書遺言となっており、それぞれに特徴があり、目的や状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言は、自分で手書きで作成する方式です。
作成日の日付、氏名、押印を明記する必要があり、これらが欠けていると無効になることがあります。ワープロやパソコンで作成したものは認められません。また、遺言の内容に不明確な部分があると、解釈を巡って相続人の間で争いが生じる可能性があるため、内容はできるだけ具体的に書くことが求められます。2020年からは、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が始まり、紛失や改ざんのリスクを避けることが可能になりました。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
本人が口頭で遺言内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2人の立ち会いのもとで正式な遺言として成立します。専門家が内容を確認しながら作成するため、形式不備によって無効になる心配が少なく、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもほとんどありません。ただし、作成には手数料がかかり、証人の準備など手間もかかるため作成する際には、事前の計画が重要となります。
どの形式で遺言書を作成する場合でも、記す内容には、遺産の分配方法、特定の財産を誰に相続させるか、相続人以外の人に遺贈する意向があるかどうかなどとなっています。また、未成年の子どもがいる場合は、後見人の指定を行うこともできます。
遺言書は一度作成して終わりではなく、状況の変化に応じて内容を見直すことも重要です。家族関係や財産の内容に変化があった場合は、新たに遺言書を作成し直すことも検討しましょう。
信頼できる専門家に相談することで、より確実な遺言書を残すことができるので、一度相談してみてはどうでしょう。